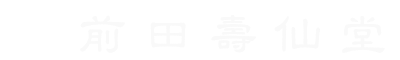どれだけ掘り起こせたのか…?

こんな年の瀬だからこそ、振り返っておきます。
2020年は大変な1年になりましたね…。
商いは大打撃でしたが、結果的に「学びの肥やし」となる1年になった気もします。
コロナだコロナだと、暗い事ばっかり言ってもしょうがありません。
気を引き締めつつ、前向きに。
あれから、もう2年…
さて、気がつけばこの投稿してから間もなく2年が経とうとしています。
「よっしゃこれ全部やろう」
あれから…
どこまで進捗したのか…
振り返ってみますか…。
「一樂會を全部掘り起こす」プロジェクト
この一樂會の第一回が行われたのが大正12年(1923)。
2023年で100周年の節目の年を迎えるので、「それまでに全部、勉強部屋で学んでやろう」という方針です。
1回~4回まで、取り上げられた「尾張の郷土美術銘柄」を列挙してみましょう。
第1回
【会期】大正12年(1923)6月18日から3日間
【展観テーマ】「五家作品陳列会」 山本自敬軒、千村伯就、正木文京、井出退歩、杉山見心
※補遺分追加
第2回
【会期】大正12年(1923)10月22日から3日間
【展観テーマ】渡辺又日庵、永井春秋園、馬場一巣、梶玄及斎、飯田布袋堂、安藤百曲園、吉田鹿助、廬山焼、豊助焼、笹嶋焼、酔雪焼、萩山焼、正三焼、有我焼
第3回
【会期】大正13年(1924)5月19日から3日間
【展観テーマ】尾張の四卿(光友・斉朝・斉荘・義宜)、高須松平家(松平義建)、竹腰篷月、御深井焼、戸山楽々園焼、玄々斎、浦蓮也、柳生流々、高田太郎庵、川村曲全斎、宗知、蝸牛庵、秋輔、原田泥亀、爲足庵の日義日経師、日潤上人、二階堂昇庵、今泉源内、朝倉自生庵、平尾数也・六代、七代、正木惣三郎、正木伊織、岡谷二珪、間宮撫松、横山鈴翁、石橋蘿窓、久田耕甫、松尾宗二
第4回
【会期】大正15年(1926)6月20日から3日間
【展観テーマ】平沢家(平沢九朗、陶斎、松伯、白駒)
次回予告
大野・西村治兵衛 治郎左衛門、濱嶋五兵衛清浄軒 道味、遠山微笑尼、清洲・早川清太夫 藤蔭翁、加島道周、瀧川一楽、氷室長翁、小寺如々庵 宗玄 省斎、松尾家代々、久田耕隆、箕田宗範、久田宗栄、久田清好、神谷別甫 西村田楽、津金庄蔵 乾斎城南坊、久野助九郎 九幡霜舎 廉卿 九兀 永日庵 正員 其律、水谷八右衛門 好山、称善、小澤列根鎭監、爰清庵、井上士朗、横井金谷、深田香實、岡谷市左衛門 無功庵巴洲 全忠、高讃寺茲明蓬生庵、白木屋武右衛門、不二山人 静遠居信天 風月雙、半介、清壽院、瀧本土休、松平庄右エ門 東亭、黒田六一郎、寺尾如水 破鏡庵、伊藤圭介、陳元贇、小澤孫左衛門 宗淳、直女笑醒、亀屋喜入 若山草結庵、大津半七 半山遮莫、大橋秋二 紫雲児 収二、常滑 青洲和尚、白鷗、長三、不二見焼、東雲焼、梅屋敷焼、菊水焼、扇山焼、西春焼、清香庵、清瓶、なるみ焼、古戦場焼、大高焼、川名焼、坂井焼、阿野焼、犬山焼、上野間焼、春古山、春琳、春暁、春宇、春丹、唐三郎、太兵衛、仁兵衛、民吉、塐仙堂、閑陸、五助、弘法善次、春厚
想像してたよりも進捗が…
あれれぇー。(;´Д`)
結構やったつもりだったんですが…なんか、すくなっ。(一楽會が取り上げた対象が多すぎる、ともいえるけど…)
御深井焼が思いのほか曲者だったせいですね、多分…。
あと3年しかないぞー…全部はさすがに無理か?
「尾張の茶の湯NEXT:補遺」をやって、その次の世代をやるか…
お茶人ばっかりじゃなく、瀬戸染付に行くか…
いや、瀬戸本業も掘り下げていかねば…
というか、やり残した常滑も回収しないと…
あぁ、地下鉄シリーズの補遺もあるねぇ…名古屋市営地下鉄では網羅できない焼き物もあるし…。
うーん…やること、多すぎ。(‘A`)
啓蒙活動はまだまだ続く…
なかなか美術・芸術に興味関心がもたれにくい世相となりつつありますが…
コッソリじっくり、地に足付けてやっていこうと思います。
何事も、コツコツやるしかないんです。がんばろー。
さて、2021年はどんな年になるのやら…このコロナ禍はしばらく続きそうな気がしています。
人が集まることが憚られるようになっても、現代の文明の利器・インターネットを使って啓蒙活動はできる。
「これでいいのだろうか?」という、迷いは相変わらずあるのですが…。
「まず知ってもらう」というステップを踏んでもらえるよう、頑張ります。