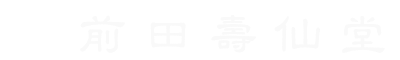御深井焼10-御庭焼と御用窯

ついに御深井焼シリーズ、10回目の勉強部屋。
長かったですねぇ…でも、もうちっとだけ続くんじゃ
ところが、それだけじゃない…「瀬戸で作らせていた尾張藩の焼き物」だけじゃない。今回はそんなお話。
毎度恒例のおさらい
という一連の流れで、「(18世紀後半~19世紀の)御深井焼は尾張藩が瀬戸で作らせた焼き物である」というお話をしてきました。
こういう例は、尾張藩だけではないんですね。
「藩からの命を受けて、陶器を生産した窯」は、他にもあります。一般的に、江戸時代のこうした「藩の庇護下にあった窯」を御用窯(ごようがま)と呼びます。
ただ、御深井焼を「御用窯」の一言で説明してしまうと、様々な誤解を生む可能性があるため、突っ込んだ説明を避けてきました。
「御深井焼は御用窯」という表現は、間違いではありません。
瀬戸は確実に「御窯屋」という制度のもと、尾張藩の庇護を受け、尾張藩の為に陶器を生産し、納めていたのですから。
ただ、「御深井焼とは何だ?」という問いに対しては、「数ある答えのうちの一つにすぎない」としか、言えないのです。
ここを勘違いして欲しくないため、こうした回りくど~い手法をとってきたのですが…過去の勉強部屋を読んでいただいた方なら、そのワケが分かっていただますかね。
つまり、「尾張藩の御用窯(瀬戸or御深井窯)」と「尾張藩の御庭焼(御深井窯)」の両方とも指し示す言葉が、「(19世紀の)御深井焼」なのです。
御用窯と似て非なるモノ
陶磁器が好き、焼き物の歴史が好き、そんな方なら「御庭焼(おにわやき)」という言葉も聞いたことがあるでしょう。
江戸時代、日本各地の大名たちの中には、巨大なお屋敷を建て、そこに広大な御庭を築き、風流を楽しんだ人たちがいました。それが国許(くにもと)であれ、別荘であれ、その御庭に焼き物の窯を築かせ、そこで好みの陶磁器を作らせる人たちも現れます。こうした実態は各地で見られました。
厳密に「御庭焼」を定義するなら…
といった感じでしょうか。
典型的なのは紀州徳川家の偕楽園焼。京都から優秀な陶工を招き、交趾写の道具を焼かせたことは有名ですね。
他には高松の理平焼や松江の楽山焼もそれに相当するでしょう。
また江戸には各地の藩邸がたくさんあり、水戸徳川家の後楽園焼、尾張徳川家の楽々園焼・戸山焼、高須松平家の魁翠園焼など短期間とはいえ御庭焼の窯がいくつも出現しています。
なんだか「御用窯」と「御庭焼」って、似ている言葉ですが、ちょっとニュアンスが違います。
御用窯は「政策・産業振興」として民間の窯を支配して作らせているのに対し、御庭焼は「趣味・数寄・エンタメ」としての要素が強く出ている、という違いを表します。さらに「御庭焼」という言葉には邸宅の近く(城・屋敷の庭)で作った、という意味も込められているのがポイント。さらに言えば、大名や家臣などによる手造の茶道具を焼いていることもポイント(※)といえます。
※必ずしも「手造をしていたこと」が「御庭焼」である条件なのではなく、「趣味としての焼き物」という立ち位置を明確にする要素の一つ。
この「御庭焼」は「御用窯」と混同しやすく、呼び分けることが難しいです。どちらも実態として「陶工(=御用焼物師)を招いて作らせている」ことが大半ですので、「御用窯」の言葉でまとめちゃっても、大きく間違いではない・・・。
ただ、もう一歩踏み込んだ表現をすれば、厳密には違う言葉なのです。
んーニホンゴって、難しいネ。細やかな表現…というのでしょうか。繊細な言葉を使いこなせる日本人でありたいものです。
「御庭焼」でもある御深井焼
「大名(もしくは家臣などを含めた武家・藩)が城内や邸内に窯を設けて、趣味性の高い陶磁器を焼かせた窯」
そもそも御深井焼のルーツは「下御深井御庭」に窯を作らせたことから始まりますよね。この時点で「御庭」の要素を満たしています。ただ、当初はどちらかというと「政治」の色が強く、贈答品を作るための窯であり、「藩主が楽しむ」というより「誰か(贈答品を送る相手)を楽しませる」ことが肝要でした。
その後、御深井の窯で「遊び、楽しみ、エンタメとしての焼き物」という立ち位置でてきたのを、覚えているでしょうか。
すでに18世紀ごろから、それらしき御庭での活動が活発になってくるのです。
そして10代藩主・斉朝のころに大きな転機を迎えます。
お殿様の楽しみ
徳川斉朝は一橋徳川家から養子として尾張家を継承したお殿様。9代宗睦が没したことで、藩主における義直以来の男系の血統が断絶したターニングポイントの人でもあります。
文政10年(1827年)、斉朝は35歳の若さで家督を斉温(9さい)に譲って、隠居します。
え…9歳の斉温に藩政を動かす能力なんてないのに、隠居なんてしちゃって大丈夫?…大丈夫なんです。
というのも…斉朝自身も幼少の頃に尾張家を相続しており、そのころから優秀な家臣たちが実質的に政務を取り仕切っていた時代なのです。斉朝は家臣からの政策提言を素直に受け入れていた、と言えば聞こえがいいでしょうが…実際のところ、あまり政治に興味がなかったのでしょうかね?他にやりたいことがあった…?だから35の若さで、家督を譲っちゃった?(やや穿った見方ですけど)
楽隠居を決めたあとは、下御深井御庭の西側に斉朝が隠居するための新御殿を作っています。そしてその前後に、御深井御庭の改造が始まったといわれています。この際、下御深井御庭にあった瀬戸山に加えて、新たに「萩島」と呼ばれる池の小島に楽焼の窯を作り、本格的な茶陶の生産を始めます。これが「萩山焼」と呼ばれる、御深井焼とは区別される尾張藩の御庭焼です。
この萩山焼だけでなく、もともとの御深井御庭にあった瀬戸山の窯も、瀬戸から招いた陶工の手によって再興されたと伝わります。(そもそも「御深井焼が中絶していた」という点に疑問が残るので、「再興」と言うべきなのか…?→「御窯屋のお仕事」)
こうした隠居後の動きを見ても、「斉朝は趣味に突っ走りたくて隠居した」と、見えますよね?
本焼(高火度焼成)の窯としての御深井焼(瀬戸山)と、楽焼(低火度焼成)の窯としての萩山焼(萩島)の2つで、好みの焼き物を作らせ、楽しんでいたと思われるのです。この2つの窯の存在は、尾張家に伝来する御庭の絵図からも明らかになっています。そして、この2つの窯に御窯屋が従事していたであろうことは、想像に難くありません。(おそらく、若き日の加藤春岱が父とともに従事していたのでしょうか)

11代斉温は病弱で、生涯を江戸藩邸で過ごした(つまり一度も尾張に来ていない)ため、斉朝は隠居後も尾張の実質的な「大殿」として、隠然たる力を持っていたといわれています。この時代が「御庭焼としての御深井焼&萩山焼」の勃興期だったのではないでしょうか。
そして12代藩主として、知止斎こと斉荘が尾張に入府。国許で過ごした期間は短いですが、尾張家伝来の名品を江戸に運ばせ、茶会を開いたり、尾張から「祖母懐土」を江戸に運ばせ、尾張藩邸の庭に窯を築き、焼き物を作らせたり(戸山焼・楽々園焼の再興)と、殿様でありつつ風雅を存分に楽しんだ人物として有名です。
また斉荘と関わりの深い、裏千家11代・玄々斎も尾張を訪れており、御深井窯で作った手造茶碗が現代に伝えられています。箱に年号があり、弘化元年(1844)に作られたことがわかっています。
※実はこの玄々斎手造茶碗にも、例の「深井瓢印」が捺されているのです……謎の多い在銘・御深井焼を探る上で、この茶碗は「ロゼッタ・ストーン」になりえる、重要な史料の一つ…かもしれません。僕が「深井瓢印こそ、名古屋城の御深井御庭で作られたものの印ではないか?」と疑っている、根拠の一つです。この印が使われていた時代推定をする基準にもなります。
この斉朝~斉荘の時代が「御庭焼としての御深井焼」の最盛期であったと考えられます。
同時に存在していた御庭焼と御用窯
こうした「藩主たちの楽しみ」が、この時代になって花開くようになったのも、前述したように「家臣たちが実質的な政務を取り仕切っていた」という側面があった上での話なのかもしれません。
一方で優秀な家臣たちは、趣味としてよりも「財政・金策」として、瀬戸の御窯屋たちに命じ、褒美として与えるための、「御深井焼」を作らせているのです。
実際、「加藤唐三郎家文書」の中に、文政8年(1825)の「御用品受注留」が残されております。年代的には斉朝の治世ですね。
これは瀬戸の御窯屋が、尾張藩からの命を受けた、焼き物の注文書。特に明記されていない部分は、もしかすると瀬戸で焼いたものもあるでしょうが、「御上覧之節」と明記されているものは、恐らく名古屋城の御深井窯で制作したものだと思われます。
※「御上覧」って何だっけ?→「衰微?再興?18世紀の御深井焼」
この中で、御城に納めるための物は「御花生」「御ふた物」といったように、必ず「御」と記されているのに対し、家臣たちからの注文品には「薄茶碗」「志野茶碗」のように、「御」は記されておらず、文字情報だけでも厳密に「区別」をしていることが分かります。
このことからも、「藩からの命で作った焼き物でも、注文主が違い、目的も違うのだろう」というのが見て取れますよね。
御深井焼が「御用窯」であり、「御庭焼」であるのは、「家臣たちの政策」と「藩主の楽しみ」が同時平行的に行われていた、ということなんです。そしてその仕事を請け負うのは、どちらも「瀬戸の御窯屋」だった。
というわけで、どちらも今日では、「御深井焼」という名称で呼ばれているのです…。
御深井焼と呼ばれる焼き物がとても作域が幅広く、そして複雑怪奇で分かりにくいのは、こんな部分も影響しているのでしょう。
「御深井焼は御用窯」「御深井焼は御庭焼」…
…このどちらも間違いではないのですが…ややこしいデスネ。(‘A`)
名工出現
「お殿様の趣味」と「家臣からの御用」で、瀬戸の御窯屋は相当たくさんの仕事を抱えていたと思われます。
そんな時勢に影響されたのか、瀬戸の陶工たちの技術レベルが飛躍的に向上。伝統的な「古瀬戸釉」や「御深井釉(灰釉)」に加え、様々な釉薬の技術が確立、もしくは復活します。
そして、その技術を自在に操る名工が、御窯屋の中から出現するのです。
それが加藤春岱。
次回は19世紀の御深井焼、御用窯に携わった人たちを、詳しく見ていこうと思います。
そして…繰り返し、お伝えします。いわゆる、業界用語でいうところの「フリ」という奴です。
…もうちっとだけ、続くんじゃ。