蝸牛と常滑・豊楽

おまっとさんです。ひっさびさの勉強部屋。
が、単発です。(後に続く可能性もありますが…)
脇道でもあり、本筋にもなりえる内容の話…。
過去に尾張の茶の湯NEXTシリーズで「河村蝸牛」を特集した際、「脇道に逸れすぎるので将来の宿題」として、触れずにいた内容を整頓して、現状報告的にご紹介します。
(追記:整頓…しきれてなくないか…コレ…まあいいや)
今回は河村蝸牛の「陶工の指導者としての側面」を深堀りします。
河村蝸牛(かわむら かぎゅう)は、江戸後期の尾張の茶人です。詳しいことは過去の勉強部屋をご覧ください。
蝸牛は好みの茶器を常滑焼、および豊楽焼で作らせていたことが、伝世の茶道具の存在から分かっています。
ただ、この分野の詳細な研究が未だされておらず、専門的な学術研究が待たれるのですが…もう個人的に探って、見解をぶっちゃけてしまおうかと。(このブログ、美術館関係者が時々アクセスしてるっぽいので、どこかの誰かがこのネタをガチで調査してくれないかなぁ…という下心もありつつ…笑)
ある人は「前田さん、あなたのブログ、超専門的な内容だからNOTEで有料記事にしても売れるよ…」とまで言われましたが…。僕文才ないし…お金貰ったら何か気軽に文章書けなくなりそうだし…。文章よりも美術品買ってください(笑)
むしろ無料でも誰にでも見られる記事として、断片的な情報でも上げておけば、いつかどこかで誰かの助けになるやも…という感覚でやってます。
蝸牛好「南蠻写」
河村蝸牛について調べている内に、焼き物と人物が極めて密接に関係していると思い、まずは「蝸牛(好)」という在銘のある焼き物を全てさらってみました。
※これより列挙する美術品はすべて「図録掲載品」として存在が写真で確認できるものばかりです。写真を転載することはできませんので、各自図録を手に入れて見て下さい(当店に遊びに来られた方なら、お見せすることができますよ)。
- 伊奈長三(初代)作 立鼓花入
- とこなめ陶の森陶芸研究所蔵
- 図録「茶の湯とやきもの(愛知県陶磁資料館・1999)」他 所載
- 底部・彫銘「日本常滑 長三作 玉春好之」
- 伊奈長三(初代)作 灰焙烙
- 個人蔵
- 図録「尾張の茶道具(愛知県陶磁資料館・2001)」「常滑市指定文化財図録第二集・陶器編」他 所載
- 見込「尾州常滑」彫、底部・彫銘「寛政丁巳五月望日 於香雲堂長三造之 蝸牛主人好之」
- 赤井陶然(初代)作 不識水指
- 個人蔵
- 図録「尾張の茶道具(愛知県陶磁資料館・2001)」所載
- 底部・彫銘「丁巳初冬 新六造 蝸牛(花押)」
- 豊楽焼(藤花園作) 南蛮写水指
- 個人蔵
- 図録「茶の湯とやきもの(愛知県陶磁資料館・1999)」所載
- 底部・彫銘「戊午初夏 藤花園造之 蝸牛(花押)」
- 豊楽焼(豊介作) 南蛮写水指
- 個人蔵
- 図録「名古屋のやきもの(愛知県陶磁資料館・1995)」所載
- 底部・彫銘「丁卯秋八月 香久連里 豊介造 蝸牛好(花押)」
ざっと5点、列挙しましたが、これらはすべて「本体に蝸牛(玉春)の名前が彫られている」という点で共通点を持ちます。
さらに「花押」を伴う作品は3点あり、これらはすべて同一人物(蝸牛本人)による彫銘であると考えられます(蝸牛作共筒茶杓に記す花押と一致します)。また、伊奈長三の灰焙烙の彫銘も「造」や「蝸牛」の筆跡から同筆であると推定できます。(※花入だけ、筆跡が違うようで…こちらは作者である長三自身による彫銘の可能性を感じています)
そしてこの順番は長三の花入を除いて「彫銘の年号の順番」になっています。
寛政丁巳五月→丁巳初冬(寛政9年・1797)→戊午初夏(寛政10年・1798)→丁卯秋八月(文化4年・1807)
分かること・推察できること
まず彫銘の筆跡が同筆であると分かると同時に、いくつかの興味深い点があります。
まず「年号(月)・季節」「作った場所・焼成地」「作った陶工の名前」「蝸牛(玉春)好」という書式(フォーマット)の共通性です。一部省略されているものもありますが、おおむね同じ順序です。筆跡である程度の「同一人物」の関与が計り知れますが、こうしたフォーマットも共通していることにより、その人物の存在を確かに感じる点でもあります。
そして年号順に並べることで、うっすらと時系列のストーリーが見えてきます。
まず蝸牛は初めに常滑の長三に好みの茶器(花入・灰器)を作らせ、その次に常滑の新六(赤井陶然)に不識の水指を作らせています。これが同じ「丁巳」の年の出来事でありながら、季節が少なくとも「五月」と「初冬」、複数回に分かれている。
そして次の「戊午」の年。従前の通説では蝸牛の生年が不明だったため、『戊午の年』がどの年であるかが不確定でしたが…過去の勉強部屋でご紹介したように、個人的研究によって蝸牛の生年推定に確信を得られたため、そこからこの「戊午」は寛政10年(1798)であると推定できました。つまり前述した花入・灰器・水指を常滑で作らせた翌年の出来事です。
この年には焼成地は不明ながら、「藤花園造之」という名前が出てきます。これが豊楽焼の2代・加藤豊八の事なのです。前述した書式(フォーマット)の順序に照らし合わせると、この「藤花園」というのは土地の名前とも、陶工の名前とも、どちらとも取れますね…。これについては後で解説[※1]します。
豊八も生年が分かっていませんが、没年だけは分かっており(享和元年(1801)歿)、この寛政10年であれば存命、史観的にも破綻がなく、納得できます。
そこから間が空いて「丁卯」の年。今度は「香久連里 豊介造」となっています。「丁卯」は文化4年(1807)で、この年には豊八は歿しており、代が変わってこれは豊楽焼の三代・豊介のことだと分かります。
一体、どこで焼かれたのか?
さて、ここからは推察の話になって来ます。まずは「どこで作ったのか?」というクエスチョン。
従来、陶工と焼成地は基本的に紐づけて考えれてきました。(例外的に別の窯に招かれ、焼き物を作っていた人の存在もいます)
つまり「長三」とか「新六」という銘があれば、それは常滑焼の陶工の名前だから「常滑で作られたモノ」であり、「藤花園」とか「豊介」という銘があれば、それは豊楽焼の陶工に関する名称だから「豊楽焼で作ったモノ」という認識がされてきました。
ですが、今回のラインナップからの考察で、一つの疑問点が生まれます。

「この南蠻写に関しては、豊楽の窯ではなく、常滑の窯で作ったモノではないか?」
問題となってくるのは、豊楽焼(藤花園作) 南蛮写水指のことです。
先述した「彫銘のフォーマット」の考察[※1]から、「藤花園」は「製作地・窯の名称」なのか「特定の陶工の名前」なのか、どちらともとれる位置にありますよね。場所の名前が省略されているのか、陶工の名前が省略されているのか…。そこから一つの疑問が生まれるのです。

「戊午初夏(豊楽の窯場に於いて)藤花園(=加藤豊八)造之」って勝手に補完してたけど…

実は「戊午初夏(常滑に於いて)藤花園(=加藤豊八)造之」って可能性もあるのではないか…
「藤花園は豊楽焼の窯場の名前である」という見方もあるかもしれませんが…やはり「造之」と後ろにくっついていることから、これは場所の名前ではなく、作った陶工を特定する名称であると考えるのが妥当と僕は考えます。(長三の場合だと「於」と前についていますし、その他にも理由があります [※後述2])
この疑問が生まれる理由は、まず見た目の違和感です。
豊楽焼では以前から「素焼き」や「楽焼」のやきものを作っていましたが、それと比較すると、この蝸牛好みの藤花園の水指はかなり焼き締まっているのです。それまで素焼きや楽焼を作っていた窯では到底焼けないような、『本格的な窯による高火度焼成ではないか?』、という疑問点です。
それに加えて、この藤花園の南蠻写の水指が、新六(赤井陶然)に作らせた不識水指と焼き上がりがとてもよく似ているのです。この2つの水指は年号順に並べると前後の関係性です。
写真を見てもらうのが一番わかりやすいのですが…ここにアップはできないので…この話はなかなか伝えにくいところです…。
移動のしやすさを考慮すると…
ちなみに、リストには挙げませんでしたが「藤花園造」の「蝸牛好南蛮水指」は他にも複数、存在を確認しております。つまり1個や2個だけじゃなく、相当数の数を同じタイミングで作っていただろうというのは確実です。そもそも焼き物を作るのに、1個や2個しか作らないというのは不自然です。
僕の想定している、想像というか妄想ではこんな感じです。
「蝸牛が常滑に赴き、複数回の試作(長三・新六)を経て、自らが好む『南蛮写』を作る焼成技法を見出し、本格的に生産するにあたって、焼き物の整形技術を評価していた豊楽焼の藤花園に『南蛮写』の焼き物を作らせた」
つまり「常滑の土・焼成技術」と「豊楽の器整形技術」を組み合わせた結果生まれたのが、蝸牛好の南蛮写だと思っています。
豊楽では到底焼けない高火度での焼成を実現するには、二通りのやり方が想定できます。「豊楽焼に本格的な窯を作る」or「常滑に豊楽の陶工を連れていき、現地で焼かせる」。どちらが容易かといえば、やはり「人間が動く」方が簡単ですよね。
イチから窯を作るのはお金や時間の面で、相当に負担の大きなものだと想像がつくでしょう。新たに作る窯の焼成に適する土や釉薬が無ければ、まるまる無駄骨になりかねない、なかなかリスキーな行為じゃないかな…?
すでに常滑で一定の水準に達していた技術(窯・適した土・焼成ノウハウ)がある(と蝸牛は分かっていた)ので、そこへ自分の好みを体現できる陶工を連れていくのが、もっとも安全かつ合理的な考え方ではないでしょうか。
例に挙げた南蛮写水指[※2]の話ででてきた、「藤花園とは、窯場の名前ではなく、陶工を指している」と考える根拠が、「藤花園に窯を新たに本格的な登り窯を作るのはちょっと考えにくい」ということでもあります。
そういうわけで「南蛮写は豊楽(香久連里の窯)ではなく、常滑で(豊楽の陶工が作って)焼かれた焼き物じゃないか?」という予測をしています。
が…結論付けるのはちょっと待って
どうやら豊楽焼の二代・豊八、三代・豊介らが蝸牛の指示で常滑に赴いて好みの茶器を作っていたらしい…
というストーリーは見えてきているのですが…どうやら「それだけではなさそう」なのです。
実は「五代・豊輔による南蛮写」も存在しているのです。
五代・豊輔は養子として豊楽焼を継いだ人で、生年が判然としていません。この人は明治まで生きた陶工なので…そこからさかのぼって、蝸牛が生きていた時代に被っているかは…ちょっと考えにくい(八十五翁の箱書の存在に頼れば、『無くも無い』程度で、豊輔が相当な長寿でなおかつ、幼少期の豊輔が最晩年の蝸牛に会っているかどうか、というレベルの怪しさ…つまりほぼクロスオーバーはしていないと思われる)。
そんな人が「南蛮写」を作っているのが、ちょっと腑に落ちません。恐らく蝸牛の直接の指導はないでしょう。
今のところ「先代たち(三代・豊介、四代・豊助)から南蛮写の技術・技法を受け継いだ」と考えるにとどまるのですが…。
そもそも「五代豊輔」の分類は正しいのかどうか、という根本的な部分から疑い始めるともう大変なことに。仮に五代だとして、この焼き物をまた同じように常滑に行って作ったのか?という部分も不明です。(今回は「河村蝸牛」という人物の軸ありきの「南蛮写」なので、その軸がどこかへ行ってしまうと途端にフワフワとつかみどころのの無い話になってきます)
先代から伝わる「南蛮写」の雰囲気を自前の楽の窯で再現しようとした、という見方もできます。となると常滑では焼いていない、ということに…。んんん…分かりづらさ、半端ないですねー。「南蛮写=常滑焼」とも言い切れない…
というわけで、最初に述べたように「現状報告的」なお話なのです。まだまだ、分からんことが多いなあ…。
これはきっと「本筋」ではない
本来…というか、従来…か?「焼き物の勉強」というのは、地域(焼成地)の歴史、技術の変遷、あるいは陶工の歴史という、骨組みの上に肉付けされていくようなものだと勝手に思っていますが…。
僕はこういう骨組みに加えて、「数寄者」というレイヤーを重ねて、物を見ています。
どこにも所属せず、大きな流れや系統もない、一個人の「好み」だけで傾向や特徴が出てくるのはかなり稀だし、確証も少なく、そのうえ曖昧なので…学術分野の人たちからすると、「確かさの無い、理解をかく乱するレイヤー」は「なるべく排除(無視)した方がいい」のかもしれません。
しかし「面白さ」を優先すると、このレイヤーは外せないのです。ある時は理解を遠ざけ、分かりづらくなるけど、外しちゃいけません。
面白さがないと、魅力がありません。
魅力がないと、他の人たちに顧みられません。
顧みられなくなると、いつしか無かったことになっちゃう。
まあ…「無かったこと」を「あったことのように勘違いする」というリスクが跳ね上がりますけどねー。その辺りが学術的に一番排除したい部分なんでしょうが…僕は学者じゃないので(笑)
結局、この手のアプローチは「間違っているかもしれない」という前提のもと、危険を冒しながらでも理解を深めようとする人たちが「楽しむもの」だと思っています。
間違ってたら、ゴメンね(笑)
「多分、合ってる」と、思うけどね…。
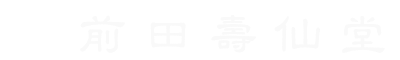


初めまして。 前津焼をクグツて辿り着きました。
次のヤフオク出品に「前津焼楽写」の箱書きがあり何処の窯かと興味を持った次第です。
前津焼にこのような作品がある可能性はあり得ますか?
(※URL)
はじめまして。
URLアドレス含むコメントは承認がないと表示されない(スパム防止)設定でしたので、しばらくコメントが表示されず失礼いたしました。
「前津焼」という箱書についてですが、「楽写」と続くことからも恐らく豊楽焼の事を指して呼んでいるのかと想像しますが、確証はありません。「豊楽を写す」ということも中にはあったかもしれませんが、僕はまだ見たことも聞いたこともありません。
逆に「豊楽焼で何かを写す」とも考えられます(こっちの方が自然かな?)。某ネットオークションのアドレスが掲載されていましたが、この手の茶碗は「暦手」といって、昔のカレンダーが基となったデザインの茶碗です。この手の茶碗は他の焼き物でも作られており、「前津の豊楽で写した」という解釈をできなくもないかもしれません。ただこれも確証がない話で、想像の域を出ません。
結局のところ、判断材料が「箱書だけ」だと想像力を働かせるしかなく、「可能性」の話をすれば「ゼロではないが……」としか言えないですね。あまりお役に立てずにすみません。