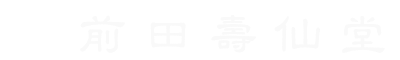名美アートフェア2025【ブース詳細】
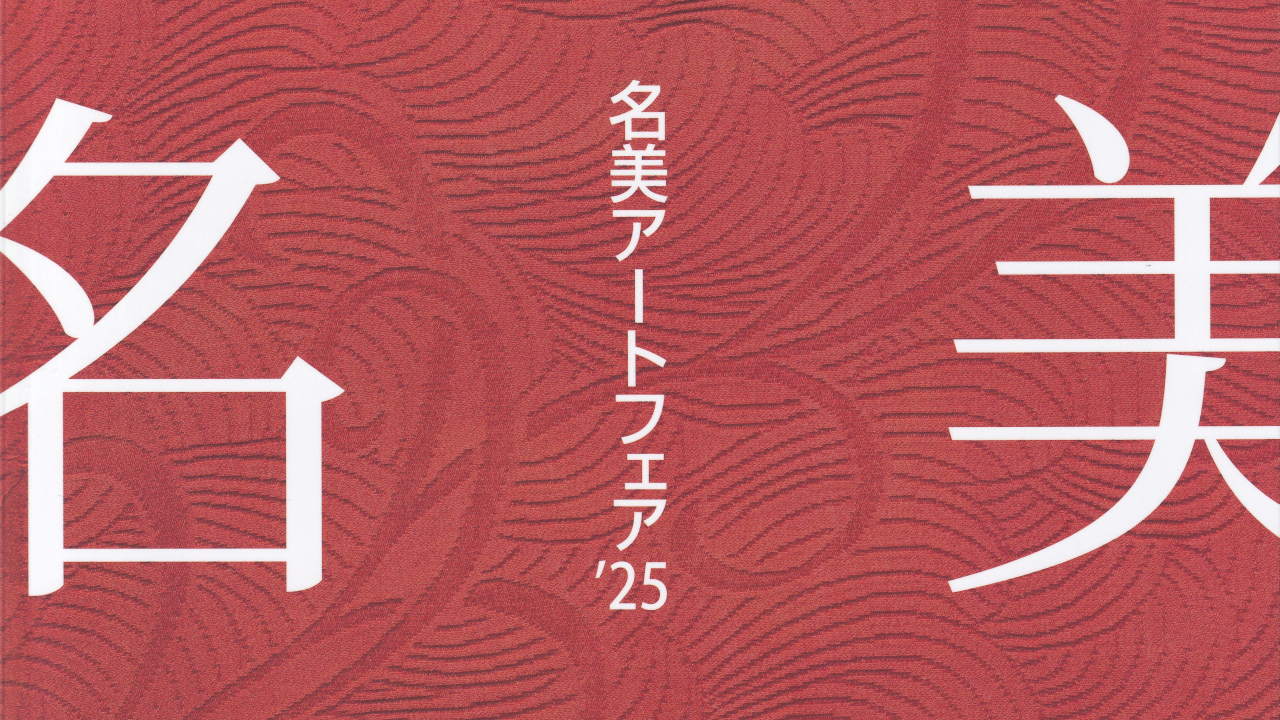
名美アートフェア2024、前田壽仙堂ブースの詳細です。
当店では毎年、郷土美術を広く皆様に親しんでいただけるよう、様々な趣向と切り口で、テーマ展示を行っております。
一昨年、名美アートフェア2023の時に「一樂會 100周年」の節目の年に際して、第一回・一樂會の特集テーマを取り上げ、それにちなんだ展示を行いました。
昨年のアートフェアでもこれに続く、第二回・一樂會のテーマを取り上げ、「尾張の楽焼」に因んだ道具を展示しました。
『一樂會とはなんぞや?』
ということは、過去の投稿をご覧いただければと思います。
第三回・一樂會の内容とは…?
予告編でもさらっと紹介しましたが…
第三回から、対象となるテーマの幅が一気に広がり、何とも収拾がつかない様相を呈しております。
尾張の四卿(光友・斉朝・斉荘・義宜)、高須松平家(松平義建)、竹腰篷月、御深井焼、戸山楽々園焼、玄々斎、浦蓮也、柳生流々、高田太郎庵、川村曲全斎、宗知、蝸牛庵、秋輔、原田泥亀、爲足庵の日義日経師、日潤上人、二階堂昇庵、今泉源内、朝倉自生庵、平尾数也・六代、七代、正木惣三郎、正木伊織、岡谷二珪、間宮撫松、横山鈴翁、石橋蘿窓、久田耕甫、松尾宗二
無茶苦茶多いのです…。
なので、過去2年は順番に一樂會の第一回、第二回と順を追ってきましたが、今年からは第三回の中でも部分的に分割して、アートフェアで特集していくことにいたします。
2025年のアートフェアでは「尾張の殿様」「高須松平家(尾張家御連枝)」「御深井焼」「戸山焼・楽々園焼」を特集します。
尾張徳川家と焼き物
御深井焼に関しては、過去に勉強部屋でしっかり取り上げましたので…特集ページから「”オフケ”ってナンダ?」をご覧ください。ダラダラ長々と説明しておるので、分かりにくいですが…。
この他に、「戸山焼」「楽々園焼」も展示いたします。これらは「尾張藩の江戸屋敷」で焼かれた焼き物。
ちょっと昔に、ブログでとりあげましたが…。覚えていますかね?
この焼き物も、江戸で作ってるけど「尾張国焼」なのです。今回は珍しいモノがいっぱいですよ。
尾張徳川家(および御連枝)についても、省略します。この手のことはウィキペディアだったり、今は簡単に調べられる世の中ですからねー。
かいつまんで要点を話しておくと…尾張徳川家は血脈を断絶させないよう、二代・光友の子、義行(高須松平家)、義昌(梁川松平家)、友著(川田窪松平家)をそれぞれ分家独立させていました。これが「御連枝(ごれんし)」と呼ばれる家です。
実際、初代~五代までが代々親子の関係性ですが、五郎太が数え3歳で亡くなって以降は、この御連枝から男系血族が尾張徳川家を継承しております。九代・宗睦の実子が夭折、また御連枝から養子に迎えた子供たちも若くして亡くなったため、徳川将軍家の分家に当たる、一橋家から斉朝を養嗣子として迎えています。(斉朝は女系で初代義直の血を引いていますが、宗睦が没した時点で男系の系統は途絶えています)
その後、斉朝は隠居し、斉温、斉荘、慶臧と尾張家の血を引かない養子として入った藩主が続きましたが、十四代の慶恕(のちの慶勝)が御連枝である高須松平家から尾張家を相続します。(ちなみにこのころの血統としては水戸家の血筋)
この高須松平家は、幕末に尾張の藩主を輩出した家ということで、尾張徳川家とは非常に強い結びつきのある家なのです。今回はこれに関連するものも展示いたします。
また、藩主ではないですが、尾張徳川家の家臣の一つに「竹腰家」という家があります。江戸後期、幕府からの押し付けの藩主が江戸で暮らしている中、尾張で実質的な政務を握っていたのは、尾張家の家臣たちでした。この竹腰家からも文化人を輩出しており、その人にまつわる品物も展示いたします。
昨年までとは、また毛色が違う展示です。皆様の御来場をお待ちしております。