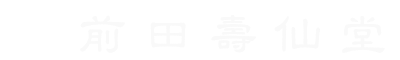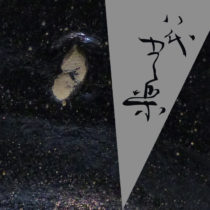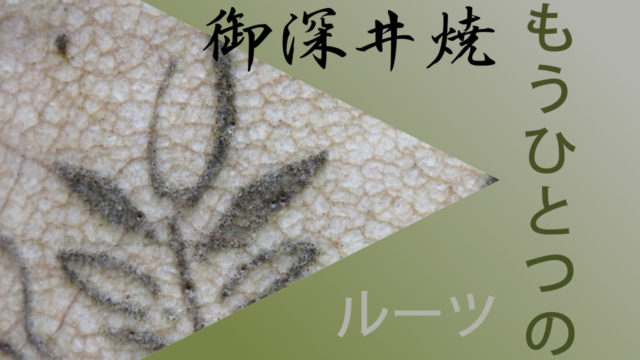特集「豊楽焼」

過去の勉強部屋をまとめました。(過去の勉強部屋ページも一部、加筆修正を行っています)
名古屋の焼き物:豊楽焼
1700年代~1920年代。
現在ではその系譜は途絶えてしまっていますが、尾張の中心部に近い場所(現在の大須・前津地域)で受け継がれてきた「豊楽焼」という焼き物があります。
素焼、焼締、南蛮写、雲華、楽焼、木具写・・・。
さまざまな陶器を生産してきた豊楽焼の歴代を特集します。
御焼物師・加藤利慶
この豊楽焼の初代とされる人物。
「御焼物師」というのは、尾張藩に仕え、製作した焼き物を藩に納めていた、という肩書き。
加藤という苗字からして、瀬戸の陶工と関連を想起しがちだが、その出自については判然としていない。
萬松寺の南・カクレサトという場所に住み、「大池」と呼ばれた人工池の畔に窯を築き、焼き物を生産していたと伝わる。
利慶の作品はあまり数が残されていないが、「不二亭」「利慶」などの印が捺された土風呂、灰器、菓子器、蓋茶碗などが現在確認されている。
前津富士見原 素焼きの藤・加藤豊八
豊楽焼の二代。
初代・利慶との関係は詳らかになっていないが、同じ墓所に「豊八」という碑名が刻まれていることから、同族と考えられている。
大池の畔とは別に、豊八は富士見原の一角に窯を築き、そこで様々な焼き物を制作していたことが文献資料にも示されている。
その窯場にあった藤が大変評判になり、人々が集まる場所となったため、この場所から窯をカクレサトに移している。
豊八の作品もあまり数は残されていないが、「豊八」の印銘が捺された作品が確認されている。
素焼きの名人・大喜豊介
豊楽焼の三代。
二代の豊八は「土細工を門弟に譲った」という文献が残されており、姓が「加藤」から「大喜」へと変わっていることからも、三代は二代との血縁関係はなかったと考えられている。三代以降、豊楽焼の代々はこの「大喜」姓を名乗り、「豊介・豊助(とよすけ)」の名を継承することになる。
江戸中期~後期の名古屋では、茶道だけでなく煎茶も多いに流行し、その影響を受けて豊楽焼でも煎茶の道具を製作している。中でも三代は涼炉(湯を沸かすための道具)を大変上手に作ると評判になり、「京師に求むるに及ばず」という賛辞を受けている。
三代と四代は制作時期が重なっており、ともに同じ「豊楽」の印を用いているため、その判別が難しい。
革新者- イノベーター - ・大喜豊助(四代)
豊楽焼の四代は歴代の中でも一際立派な墓が作られており、多大な功績を残した人物と目されている。
焼き物の表面に漆を塗り、蒔絵や漆絵を施し、あたかもそれが「漆器」のような「陶器」、木具写(きぐうつし)。
素焼き、南蛮写、楽焼に加え、これまでにない斬新な陶器も創出し、一躍「豊楽焼」の名を高めたであろう新技法。
三代と四代で制作時期が重なっており、判別が難しいといわれるが、この木具写に関してはこの四代から始まったと考えられている。
偉大な師を受け継ぐ・大喜豊助(五代)
四代・豊助は比較的若くして亡くなったため、幼い嗣子(徳三郎)が成長するまでの間、養子として入った五代・豊助。
出自は明らかではないが、恐らく豊楽焼に従事した優れた陶工の一人だったと考えられている。
好評だった木具写をさらに洗練させ、華やかな蒔絵、そして釉下彩の技術も向上、より品の良い製品を世に送り出した。
「木具」という枠組みに問わられず、水指や花生などまでもこの技法で作り始めている。
出色の木具写・慶楽焼
もとは豊楽焼に従事した陶工が独立し、1代にかぎって「慶楽焼」を作っていた。
精細緻密な蒔絵の技術に目を引かれるが、かりっとした釉下彩を引きだす焼成技術も高い。
非常に豪華な蒔絵は、背後に強力なパトロンの存在を匂わせ、窯の場所もかの龍門の近くにあったと言われる。
転換期のデザイナー・大喜豊助(六代)
偉大な革新者、四代豊助の血を引く、六代豊助。
明治維新を迎え、「藩の庇護のもとにある一介の陶工」から「産業としての陶芸家」への転換を余儀なくされた時代に、積極的に豊楽焼の進化を促した人物。
「万国博覧会」への出品など、技術の粋を結集した「1点もの」が生産されたのはこのころから。
しかし他方では実用的な茶陶も引き続き生産している。数種類の印銘が知られ、数は比較的多い。
那古野焼・大喜豊助(七代)
六代豊助の長男。精力的に豊楽焼を盛り立てる父のもとで成長。
大正初年ごろ、那古野神社で行われた観桜に会訪れた茶人や画家など、名士たちが絵付けを施した楽焼の生産に携わっていたことが知られ、これが今のところ「七代作」とわかる作品の一類。
七代は40歳の若さで父(六代)よりも先にこの世を去っているため、作品は非常に少ない。
豊楽焼最後の人・大喜豊助(八代)
六代豊助の次男。七代の弟。兄の逝去によって、豊楽焼を継承。
兄(七代)、父(六代)が相次いで亡くなり、非常に苦しい状況に立たされていたと考えられる。
江戸時代から名古屋に続く窯元を盛り上げようと、一樂會などの地元の有志の人たちに支えられながら、楽茶碗などを制作していた。
しかし大正14年、八代も40を迎える前に亡くなってしまい、ここに豊楽焼の命脈が尽きてしまう。