郷土の焼き物-豊楽焼・三代、四代

ちょっと間が開きましたが…ゆっくりノンビリやっていきます。
「郷土の焼き物」豊楽編。歴代を順にご紹介していきます。
加筆修正
※一部コンテンツを商品紹介ページへ抜粋・加筆修正(2017/12/18)
※さらに一部加筆修正(2018/10/31)
「京師に求むるに及ばず」
初代・利慶、二代・豊八と続いた豊楽焼。前回ご紹介したように、二代・豊八は門人に代を譲り、三代からは「大喜豊介(豊助)」が豊楽焼を継いでいます。
資料によっては「豊八の子、豊助(三代)」となっているものもありますが…墓所が初代・二代とは別のお寺に移っていることや、「加藤」姓から「大喜」姓になっていることからも、恐らく親子の関係ではなかった、という説が有力です。
三代・豊介は安永8年(1779)生まれ、元治元年(1864)歿。江戸後期の人。
このころになると、茶の湯ブームに続いて、煎茶も流行の波がやってくるのです。柳下亭嵐翠(りゅうかてい らんすい)という名古屋の人が、豊助の製作する煎茶道具について絶賛しています。
詳細は省きますが、見出しに持ってきた「京師に求むるに及ばず」というのは、煎茶道具(瓶掛・涼炉など)を豊介が大変上手に作るため、このような賞賛をしているのです。やはり当時は京都の物というだけで、一級品。みんなの憧れ。豊介が作れば、その京都に品物を求めなくともいい、というのは最上級の褒め言葉ですよね。
三代・豊介の作品
前回、二代・豊八のときにも紹介した「尾張年中行事絵抄」(1818-1844年頃成立)を引用すると
…爰(ここ)に来住して茶碗其外いろいろの土細工をなす 甚工(たく)みなりし 但し瀬戸の如き薬はかけず それゆへに素焼の名を得たり 其庭に植たりし藤次第次第にうつくしく咲て いつとなく諸人の遊観する所となれり其後 土細工を門弟にゆづりしよし…
「尾張年中行事絵抄」(1818-1844年頃成立)
と、もともと二代のころより釉薬の掛かっていない、「素焼き」の焼き物を作ることで著名であったことが分かります。また同時期に「弟子」として三代豊介も制作にかかわっていたことは想像に難くありませんし、実際に三代・豊介の作品にも「南蛮写」の茶陶がいくつか有ります。商品紹介ページでご紹介したこの水指も、三代豊介によるものです。
無釉陶だけでなく、緑釉を掛け流した織部風の菓子器や、雲華焼の灰器なども製作しています。(雲華焼については後ほどご紹介)
そして三代はこれまでの利慶や豊八とは違った作風も確立しており、特筆すべきは素焼きの陶器の上に岩絵具で絵付けを施した作品です。器形は菓子器や棗、瓶掛や手焙など。金箔や銀箔で彩られ、色鮮やかな美しい草花は田中訥言、近藤芙山、渡辺清など、尾張の著名な絵師によって描かれています。
雲華焼とは
商品紹介ページにて、三代豊介の共箱が沿った雲華焼の灰器をご紹介してます。
劇的進化・豊楽焼
今回は三代と併せて、四代もご紹介。
四代・豊助は文化10年(1813)生まれ、安政5年(1857)歿。先代の父・豊介よりも先に亡くなっています。
制作時期が三代と被っており、先述の通り同じ「豊楽」の印を用いており、さらにどちらも「トヨスケ(豊介・豊助)」と呼ばれていることから、正確に作品を分類するのが非常に困難です…。製品は四代が作り、箱は三代が書いているもの、またはその逆も当然あるはずだと考えられ、箱書のみによる判定も難しいです。
四代・豊助は豊楽焼の中でも偉大な功績を残した人として、ひときわ立派なお墓が作られており、その功績こそが「木具写」の創始だと考えられています。
先述した三代・豊介が始めた、「素焼きの器の表面に岩絵の具で絵付けを施した作品」は四代も製作していますが、それからさらに発展・進化を遂げたのが「木具写」です。
木具写
木具写とは、「木製の器を写して造られた陶器」の意味です。主な器は棗・八寸・蓋物碗・段重など。本来、これらの器は木地のものですが、これを陶器で造ってしまったのが「木具写」なのです。
一見すると、木地の漆器のように見えるが、手にとってみると、わずかに重い。
蓋を開けて中を見ると、織部釉の掛け流しと草花の絵付けがあり、そこ始めて「ああ、これは陶器なんだ」と気づく趣向。思わず「おっ」と言ってしまうサプライズ演出。
それまでにも「陶器の表面に漆を塗って磨いて仕上げる」といった技法は、土風炉などに用いられていました。ただし「木製品を陶器で写す」という斬新なことを始めたのはこの四代・豊助から。この木具写が大変評判になり、その後の歴代豊助も木具写を製作。豊楽の代名詞的な器となったのです。
こうした凝った作品を作るのには、非常にお金が掛かることが想像できます。(塗の仕事は恐らく塗師に外注しているため、単純に手間(人件費)や素材の原価だけでもコストが非常にかかっているはず)豊楽の初代より「御焼物師」として、尾張藩の御用を受けていた豊楽だからこそできた、高級品だといえます。
商品紹介ページにて、四代豊介の共箱が沿った木具写の盃台をご紹介してます。
「瀬戸の半助」との関係
※2018/10/31追記
実は「木具写」と呼ばれるものには、「陶胎」と「磁胎」のものが存在します。つまりベースが「陶器」のものと「磁器」のものです。
外側からだと漆が塗られ、蒔絵が施されて殆ど同じように見えますが、中を見ると「緑釉の掛け流しや鉄絵」があるのが陶器、呉須の染付によって絵付けが施されているのは磁器。驚くほどこの両者は似通っているので、この「塗漆」と「蒔絵」の仕事をした職人は同一人物、もしくは同一の工房だった可能性が指摘されています。
しかし豊楽の窯で「磁器を生産した」という記録は残されておりません。楽焼と磁器では、焼成温度が違いすぎます。木具写の創始者と目される、四代豊助の生きた時代(1813-57)は、ちょうど瀬戸で染付磁器の生産が始められた時期と一致します。ゆえにそう簡単に豊楽の窯で磁器を生産できるとは考えにくいのです。
そして「磁胎木具写」の製品の中に、「川本半助」の共箱に入ったものがいくつか知られます。この半介は四代目。生年は不詳ながら、文化年間に家業を継いでおり、安政4年に歿している。生きた時代は四代豊楽と奇妙に一致する。
さらに「豊」の文字が呉須によって高台内に書き付けられた磁器も存在します。これは四代豊助の作といわれ、瀬戸に赴いて豊助が絵付けを施し、焼成したものだと考えられています。(豊楽で染付は焼けない)
つまり、四代・大喜豊助と、四代・川本半介は交流があった可能性があります。
この「磁胎木具写」は豊楽で制作された木具写を見た瀬戸の半介が、「磁器でもできないか」と技術支援を受けるため、瀬戸に四代豊助を招き、漆を定着させる素焼きの技法を学んだのではないかと思われます。
しかし実際、染付の器に漆を定着させるのは非常に困難だったようで、僅か数年でこの磁器での木具写は作られなくなったと考えられています。(世に伝わる磁胎の木具写が非常に少ない)
(「陶胎」の豊楽が先だった、「磁胎」の半介が先だった、という両方の説はあります)

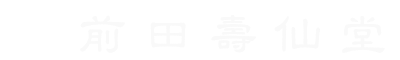






偶然入手した豊楽焼は、「陶器」のもので外側は丹念に漆で絵付けされ、中を見ると緑釉の掛け流しで松の鉄絵があります。名や刻印はありません。 箱書きは「金襴手 扇面形菓子器 名古屋 半介 花押」となっております。「名古屋 半介」は「瀬戸の半助」や「豊助」とどのような関係にあたる人物でしょうか?ご教授頂ければ有難く存じます。
こんにちは。
文字情報だけでは断定的なことは特に言えませんよ…と、前置きをしておきます。
察するに「陶胎木具写の器」が「金襴手 半介」と書かれた箱に「合わせ」て入れてあるのだと思います。恐らくネットの検索でウチのページにたどり着いたのだと思われますが、ブログ記事の後半追記部分をよくお読みください。川本半介は瀬戸の染付磁器を作る窯であり、半介の箱で「金襴手」と書かれているのであれば、箱の中身は木具写だとしても「磁胎木具写」であるべきだと思います。なので、この場合は箱と中身の違う「合わせ箱かな?」というのが、文字だけから推測した感想です。「名古屋 半介」というのがどういう人物かは、正直僕もよくわかりません。
もし「写真で詳しく見てほしい」というご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせフォームより一度ご連絡をください。