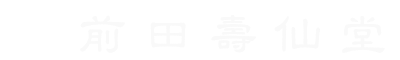海を渡る瀬戸染付02:焼き物イノベーション

すっかり間が空いてしまいました…。
短期集中と言っておきながら…平気で1か月以上ほったらかしに…。
なんかもう「フリ」に対する、「お約束」みたいな流れで申し訳ないです。<(_ _)>
個人的に気になることがあると、そっちばっかり調べちゃってねー…ブログの方がおざなりに。
例によって、今年もやります、夏の自由研究…そのうち「道草」タグでアップしますよ。
…さて、瀬戸染付の続きです。
幕末の開国で外国人商人との商いが増え、明治維新からのパラダイムシフトで大きく構造を変えていく日本社会。
その中で「瀬戸」はどんな立ち回りをしたのか。今回から焼き物に関わる話に入ってきます。
今回はまず「瀬戸染付が始まるサワリの部分」をご紹介します。
維新前の瀬戸の状況
染付磁器に限らず、広域的な意味での「江戸時代の瀬戸の窯業(焼き物)」は、基本的に尾張藩の保護下にありました。
瀬戸は戦国時代に「瀬戸山離散」と呼ばれる、極端に窯が減少した時期がありましたが、尾張藩成立後に職人たちを瀬戸に呼び戻し、陶器生産が奨励されました。(「御深井焼」でこの話のサワリは触れてますね)ここから、尾張藩庇護下の瀬戸の陶器生産が続いていきます。
そして享和年間(1801-04)に、瀬戸で初めて染付磁器が作られ、陶器生産から磁器生産に転業する窯屋が出現します。
平安時代までさかのぼる非常に長ーーーい瀬戸の歴史を鑑みれば…これまでは陶器生産が主流であり、瀬戸にとって磁器生産はとっても新しい技術なのです。
瀬戸新製
いつからこう呼ばれたかは不明ですが…瀬戸の染付磁器を指して「瀬戸新製」という呼称も、そういう背景があって生まれたものでしょう。
ある日を境に突然、瀬戸で作られる焼き物が磁器生産にガラッと変わったわけではなく、一部の窯屋が磁器生産に転向しましたが、引き続き陶器の生産も続けられます。ですので、陶器生産の方は瀬戸では「本業」とも呼ばれました。
複合的な事情
そもそも、なぜ瀬戸で染付焼が始まったのか、というお話は非常に複雑に絡み合っております。
瀬戸の窯業の歴史を鑑みるに、『今は主流じゃなくても、先見的な価値観で、魅力や優位性を見出し、いち早く取り入れる。』そういう気概を持っていた、「新進気鋭な人たち」が、瀬戸で磁器生産に転向した窯屋だった、と僕は勝手にイメージしています。
まず「瀬戸の窯屋が尾張藩の保護政策下にある」ということを細かーく説明すると、これがまた長ーくなるのですが…。誤解を恐れずに言うと、「瀬戸の窯業が尾張藩におんぶにだっこだった、という訳ではなさそう」ということ。
要するに、ある程度の食い扶持は保証されているけど、過度な生産をセーブして、競争を抑制するシステムが働いていたということです。どちらかというと、支援というより統制・規制といったほうがいいかもしれません。窯屋の息子は長男しか家を継げず、むやみに陶器生産業者が増えることを抑制していたようです。瀬戸で染付が作られる前の江戸中期ごろには、肥前の磁器が日本各地に流通し始め、瀬戸の陶器はそれに押されて売り上げが鈍っていたとも言われます。(実際景気がどうだったか、当時のデータを調べたわけではないのですが、モノの本にはそう書いてあったので…)
そんな状況では、旧来の生産者たちが「保守的」になるのは必然的で、なおかつ新規参入が難しい世界となります。競争を排除し、既存の生産者を守る仕組みですからね。それが長く続いて「言われたことだけやってりゃいい」「あんまり焼き物作っちゃイカン」となれば、いろいろと停滞を招いてしまうものです。かといって、そういう人たちばかりとも限りませんよね。
そこで「染付磁器」の技術革新です。「何か新しいこと、やりたい!切り拓きたい!」という抑圧された意欲をぶちまける、いい対象ですよね。停滞の中に生まれた、こんな感じのフロンティアスピリットがうまく作用したのだと思います。(まあ、これは勝手な想像です)
さらに尾張藩も、この新しく興った焼き物に「専売制度」を導入して、生産・流通を藩の統制下に置き、より強力に窯屋をバックアップする体制になります。流通に藩が介入することで、窯屋は制作に集中し、銭回りをよくして、なおかつ藩は冥加金を得て、藩の財政にも寄与する理想的な関係になります。今風に言うと「利権」ってヤツです。
様々な複合的な理由がからみ、重なり、瀬戸で「新進気鋭な人たち」が生まれてくる、イノベーションが起きる土壌が出来上がっていたと思われます。
瀬戸染付イノベーション
さて、具体的にどんなことが起きてたのか…。
かなり端折りながら、焼き物の技術的な部分だけピックアップしてみます(細かく全部やると、長すぎる)
伊万里焼・有田焼の磁器で有名な肥前有田では、磁器の原材料となる良質な「陶石」が産出し、これを細かく砕いて水で練って粘土にします。この陶石のすごいところは、磁器特有の硬質な素地に必要な成分が、これ単味でほぼ賄えてしまうところ。
ブラタモリでもやってましたねー、変質流紋岩火砕岩。地質学で焼き物を知るという、メチャクチャ斬新な切り口の回でしたなー。
しかし瀬戸ではこの陶石のような便利な石は産出しませんでした。よって、さまざまな粘土・珪石・長石を配合して、複合素地とするしか方法がありません。磁器に適した素材の探索、ちょうどいい配合、その試行錯誤が繰り返され、やがて独特の光沢のある素地の配合が完成します。
一方、染付磁器に欠かせない青い絵付けの元となる「呉須」は、肥前有田では長崎から輸入されたものを用いていましたが、瀬戸では地元で天然呉須が山の中から取れることが以前より分かっており、「地呉須」「山呉須」「砂絵」などと呼ばれていました。これが伊万里とは違う、初期瀬戸染付の特徴の一つと言える「呉須」の独特の発色に繋がるわけです。
瀬戸村庄屋・焼物取締役の加藤唐左衛門が中心となって、付近一帯から盛んに掘り出すことになります。(のちに染付の生産が盛んになると、呉須が不足し、長崎から唐呉須を買い入れて、それと混ぜて使うようになります)
釉薬も初めは呉須の絵付けがにじんだり、流れたりしてしまっていたのを、「灰の種類」を変えたり配合を変えながら、独特の青みがかったツヤのある釉薬が完成します。
また分業制が確立されて、磁器生産においても土成形・絵付けを専門に行う職人たちが腕を振るい、高品質な染付磁器が大量に作られるよう、発展してきます。
この染付磁器の技術革新…多分とんでもないスピードで進んでいたと思われます。わずか数十年のスパンで、技術力の高まりが半端じゃない。これもひとえに瀬戸で窯業に従事する人たちの情熱と、尾張藩の専売制度による銭回りの円滑化が大きく寄与している気がします。
まさに「イノベーション」と呼べるものだったと想像します。
「サワリでこのボリュームかよ…」
と、引いてる人もいそうですが…笑
これが江戸中期~後期にかけて、瀬戸で染付が作られるようになって発展していくサワリです。なんかもうサワっているのか、書いてる自分もよく解らんのですが…。
「瀬戸で染付磁器が作られるようになるまでのストーリー」は、アッチコッチでいろいろ語られています。物語として脚色された部分と、事実関係がゴチャゴチャしており、今一度この部分を整理し、見直す必要があるのではないか?と言われています。なので僕はフワッ(?)とした感じでしか、まとめておりません。(つーか、むしろ独自すぎる脚色つけててるような…?)
この「瀬戸染付の黎明」は、今後研究が待たれる濃ゆ~い分野なのです。
民吉生誕250年・歿後200年の節目を控え、2022年~2024年に何が起こるのか…楽しみですねー。( ´∀`)
次回は、海外向け製品のイノベーションを起こした、「イノベーターたち」にフォーカスを絞っていきます。
瀬戸で生まれたイノベーターたちのもとへ、明治になって、東京から新進気鋭な人たちがやってきます。