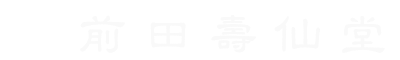海を渡る瀬戸染付03:交錯するイノベーターたち

随分、間が空いてしまいましたが…。何事もなかったかのように、再開いたします…。
維新前後の「海外へ向けた産業のうねり」と、瀬戸での「技術革新」のお話が、明治以降に絡み合ってきます。
輸出品を画策するイノベーターたち
実は維新前から、すでに輸出品を作る動きが瀬戸では見られています。
安政5年(1858)、三井組が舶来見本70~80種をもって瀬戸を訪れ、加藤兼助に貿易品の生産依頼したのが、瀬戸では一番早い例だといわれます。これは横浜が開港される前年…やはり、先見性を持った人たちは動きが速いですねー。
また文久元年(1861)には、名古屋堀川端筋の「角吉」から瀬戸物惣代の御蔵所へコーヒー碗などが注文された記録が残されています。文久3年には再び三井組が輸出見本を数種類、瀬戸で作らせています。
このように…維新前から早くも瀬戸では「海外向け」を志向する動きがみられ、試行錯誤が重ねられた時期が続いたと思われます。
万国博覧会で世界と繋がる
そして明治維新を迎え、尾張藩の庇護がなくなると、自由になった反面、自立が求められる時代になります。
もともと「新進気鋭な」瀬戸新製の窯屋たちは、維新前から「輸出向け食器」の需要を肌で感じ取っていたのか、この自立に向けた動きが早かったのでしょうか…。
明治6年(1873)のウィーン万国博覧会(オーストリア)は、明治政府が初めて正式に参加した国際博覧会(万博)です。戦争で消失する前の名古屋城天守閣の金シャチも、このウィーン万博に出品されています(今年、地上に降ろされ、ペタペタ触られ、お城のためにお金を稼いでくれたのは、戦後に作られた2代目金シャチです)
ウィーン万博は「新しくなった日本を全世界に喧伝する」という使命を帯びていました。工芸品(浮世絵・染織品・漆器・櫛・人形)、美術品(仏像・楽器・刀剣・甲冑・陶磁器)、さらに生活用品から、国宝級のもの、極めつけは神社と日本庭園まで……日本中のありとあらゆるモノ(まさに万物)をウィーンに運び、展示しました。
ここの「陶磁器」の中には、先行してパリ万博(1867年)に参加していた薩摩や伊万里だけでなく、瀬戸も含まれていました。
この万博への参加を契機に、国内の殖産振興、瀬戸における陶磁器の輸出に向けた動きが加速していきます。
ウィーン万博で伝習生(西洋の技術を学ぶために日本から派遣した技術者たち)が持ち帰った、「石膏型による製法」の導入が瀬戸でも進み、酸化コバルト(科学呉須)の技術も定着します。そして明治9年(1876)のフィラデルフィア万博(アメリカ)や、明治11年(1878)のパリ万博には、さらに多くの瀬戸の窯屋が出品し、非常に高い評価を受けています。
海外から新たな技術を取り入れ、また窯屋同士で連携して、陶磁器の技術研究が盛んに行われていたのです。
ここでようやくクロスする
この明治9年~明治11年が、初回にお話した「森村組」が設立された年になります。ニューヨークではまだ雑貨屋さんだったころの「日の出商会」。
これらの博覧会の前後から、海外でも「日本製の陶磁器」への関心が高まっていったように思います。明治16年(1883)には、ニューヨークのモリムラブラザーズから「こういうものが大量に売れるから、日本で同じようなものを作ってくれ」と、見本としてフランス製のコーヒー茶碗を日本に送ったという出来事は、そういう海外の関心を表す、端的な出来後だったと思われます。
日本初六人組コーヒー具
森村組の大倉孫兵衛は、前述のニューヨークからの注文を受け、京都など各地の窯元を訪ねて、コーヒー碗の試作を依頼します。
しかし「取っ手の付いた茶碗」は、当時の日本ではまだ馴染みがなく、なかなか快く受け入れてくれなかったようですね。瀬戸でようやく、試作を受け入れてくれる人物と出会います。それが当時の瀬戸で技術研鑽の中心的人物であった、川本桝吉(初代)・川本半介(六代)たちでした。
川本桝吉
川本桝吉は高い技術力を買われ、「五代半介」として川本半介家に養子に入った人物です。最初にご紹介した、維新前より始まっていた貿易品の試作にも関わっています。文久2年(1862)、六代半介に代を譲って独立し「北半」「奇陶軒」などと号して、明治以降も染付磁器の生産を行っていました。
また先述のウィーン万博以降に日本に伝わった、海外の新しい技術「石膏型」を伝えるため、桝吉の自宅に「伝習所」を設け、そこに技術者を招いて希望者に広く石膏型の技術を伝えるなど、瀬戸での磁器生産の技術革新を進めた中心的人物でした。
桝吉らは森村組からの要望に応え、コーヒー具(カップ・ソーサー・ミルクポットなど)を試作し、ニューヨークへ送られました。
過熱する陶磁器製造…混乱と変革
当時、このような陶磁器の輸出を画策したのは…何も森村組だけではありません。他にもいます。
先述したように、維新前から既に輸出品製造を目指した動きは始まっており、維新後はさらにこの規模が拡大、あちこちで進みはじめます。森村組はその一部分のお話であり、また瀬戸以外の窯業地でもこうした動きは当然ありました。(京都・錦光山惣兵衛、横浜・真葛窯などなど)
陶磁器の製造需要が飛躍的に高まった結果、どうなったか…?
過当競争・生産過剰となってしまうんですね。完全に想像ですが、市場規模や需要を顧みず、業界全体の動向も気にせず、個々が好き勝手に製造しまくってしまった、といった感じなんでしょうか…。
さらに過熱した競争から粗製濫造を招き、品質が低下すれば価格暴落を招き、明治15年~18年の間、日本中の窯業は不況を引き起こしてしまいます。
恐らく…維新後間もないこの時代、陶磁器の生産に従事する人たちに、世界を股にかけた資本経済のバランス感覚があるはずもなく…製造を制御する社会構造が未成熟だったことが招いた不幸だったのだろうと思います。
約売注文と専属契約
その反動なのか…明治18年(1885)より、モリムラブラザーズは大口顧客に対する「インポートオーダー(約売注文)」を開始します。
製品の量産前に売り先を確約(契約してから必要な数を発注)することで、運転資金の回転効率が上がり、かつ取引先(瀬戸の製造者たち)に対する仕入れも有利になり、安く仕入れることが可能になりました。仕入(生産)と卸売を一貫して営む強み、というやつですね。製造業者サイドとしても、あらかじめ売れる数が分かっているので、余剰生産をせず効率的な生産が可能になり、さぞ助かったことでしょう。
江戸時代まで長らく続いてきた、陶磁器生産の差配を「窯屋ごとにお任せ」だった状況からの変革と言えます。大量の輸出製品を安定的に確保するため、より産業的な構造になったわけです。
明治25年(1892)に、より瀬戸の窯屋との綿密な連携を図るため、森村組・名古屋支店を開設します。その翌年(1893)には、川本桝吉、加藤五助、加藤周兵衛などの窯屋たちと、「手窯」と呼ばれる専属契約を結びます。この専属窯は素地(磁器のボディ)の確保を目的とし、これとは別に森村組と専属契約した「絵付け工場」との連携を森村組が差配することで、より効率的で大規模な生産体制を実現したのです。
これにより高品質な陶磁器を確保し、飛躍的に輸出量を増やし、後に日本の対米陶磁器輸出の4分の1を森村組が占めるまでに至ったのです。
森村組の手窯を担った窯屋たち
ようやく、ようやく…ここまでたどり着けました。
森村組の手窯として契約した、加藤五助、加藤周兵衛。
「やたらとデザインが似通った別々の窯屋」が、ここでようやっとでてきました(笑)
今回はなんだか、歴史と文化の話の中に、さらに経営学・経済学チックなお話まで交じって、チョットつまんない感じになってしまいましたが…。
次回はこの二つの窯屋を掘り下げます。