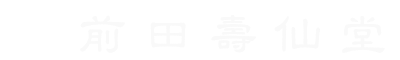尾張の茶の湯NEXT(補遺):尾張の余技作家

数年前にやった、「尾張の茶の湯NEXT」シリーズの「補遺」編をやろうと思います。
先日、名美アートフェアで開催した「Revival 一樂會」の第1回で取り上げた、尾張の余技作家5家のうちの、NEXTシリーズで紹介することができていなかった、正木文京、山本自敬軒、井出退甫について、それぞれ御紹介をしていきます。
その前に…
余技作家
「余技作家」という呼び方は、あまり一般的ではないかも知れません。
要は「専門の陶工・陶芸家ではないけれど、趣味や楽しみ(=余技)で作陶をしている人」の事です。「作家(=プロフェッショナル・職人)」ではないけれど、風情や雅味のある良い作品を作っている人たちを「素人」と呼ばずに、敬意を払って呼ぶと「余技作家」となるわけです。
茶の湯の世界では、好き(数寄)が高じて、こうした作陶活動に傾倒する人はしばしば現れます。つまり大抵の余技作家は「茶人・数寄者」でもあります。
過去の勉強部屋でも述べたように、陶芸に関して素人同然の茶人が、いきなり「好きが高じて焼き物を作れるようになる」ワケがありません。
作陶は「よっしゃあ、陶芸やるぞ!」と、そんな簡単に始められるものじゃない…というのは想像できますよね?余りある財力があり、多数の人を動かせる権力者であれば「御庭焼」ということが可能でしょうが、余技作家とはそういう人たちではありません。焼き物の窯、あるいは陶芸家とのコネクションがあり、その窯を借りて作品の焼成をスタートする人が大半です。
もっとも古く、そして有名な例が本阿弥光悦でしょう。光悦は本職が刀剣の鑑定・研磨などを生業としていましたが、陶芸作品も高い評価を受けています。この陶芸作品は、一から自分で始めたものではなく、田中常慶・楽道入(ノンコウ)の手ほどきを受け、楽家の窯で焼成したと考えられています。
造れる人は限られ、名を残す人はさらに数少ない…
有名無名を問わず、作陶を楽しんだ人は、その時代ごとに存在していたと思われます。
が…そのすべてが現在にまで伝わっているわけではありません。
その理由はいくつもあり、まず「陶工とのコネクションができる人は、かなり限られる」という点で高いハードルがあります。焼き物の窯は「土・水・燃料」が揃い、かつ適した環境が無ければ、窯業は成り立ちません。身近に作陶ができる環境があるとは限らないので、余技として陶芸をスタートできる人自体が絶対的に少数なのです。
その環境があったとしても、あくまで自分の楽しみのために作っている(=生業としてではない)作品なので、数自体がそこまで多く作られているわけではないのです。1度か2度か、自分が使う分を作れば、大抵は終わってしまいます。「友人に贈り物として作る器物」とかを作り出せば、数が増えていくでしょうけどね。
そして最後の高い障壁。作品そのものに魅力がなければ、価値を帯びず、時代の流れの中で失われ、忘れ去られていくものなのです。
100年、200年、300年と長い年月を経て、作品・作者の名前が後世に伝えられていくということは、とてもすごい事なんです。
江戸中期から現れる、尾張の余技作家たち
そんな珍しい「余技作家」が、尾張では江戸時代中盤から続々と現れます。
山本自敬軒・香西文京・千村伯就・井出退甫・杉山見心・平沢九朗・市江鳳造・正木惣三郎・正木伊織・安藤百曲・横山鈴翁・今泉子日庵・大橋秋二・風花翁雲阿…江戸時代という括りだけで、こんなにも…。
これは全国的に見ても、かなり特異な性質と言えます。一介の茶人の来歴だけでなく、その人の手造りの作品も、程度の差こそあれ現代に伝わっていること自体が稀なのに、尾張はその数・例がとても多いのです。
これには尾張の土地柄が大きく影響していると思われます。
尾張で余技作家が次々出てきたワケ
まず一番のボトルネックとなる「窯業地」の問題。これが他の地域に比べて極めて優位な立場にあったといえます。
瀬戸(美濃)・常滑という、古くから続く本格的な窯業地を抱え、さらには藩としても御深井焼・萩山焼などのお庭焼の制作をしており、また市中では豊楽焼や笹島焼といった楽焼の窯も起こり、江戸中期以降の尾張は多様な焼き物を制作するベースが発展していた稀有な土地柄なのです。
中でも尾張藩が瀬戸の陶工を庇護していたことが大きかったと思われ、藩と竃屋のつながりから、自然と茶を嗜む武士と、瀬戸の陶工が関わる例が多かったのだろうと想像ができます(実際、余技作家として上に列記した人物は尾張藩士が多数います)。
大抵、江戸時代の「茶人の手造の茶器」というものは、比較的簡素な窯で作れる「楽焼が多い」のですが…尾張の余技作家たちの作品を見渡すと、高火度焼成の窯で作った、「本格的な陶器の作品が多い」のも特色です。やはり瀬戸という窯業地の存在が大きいといえます。
また別の側面としては、江戸中期に尾張では爆発的に茶の湯が流行したという側面があります。
これは武士に限った話ではなく、町人の間でも茶の湯を楽しむ人たちが急激に増えています。名古屋城下の特異な町割り(城下に商人の町が発展し、その外側に武士の長屋があるという、他の地域では見られない計画的な町割り)のせいか、武士と町人が茶の湯を通じて交友しており、極めて独特な茶の湯文化が花開いていたと思われます。
茶の湯が急激に流行することで、ある問題が生じていたと想像できます。それは茶道具の不足。
「お茶が飲めれば何でもいい」という訳にはいきませんし、「古い伝来の茶道具」というのは絶対数が少なく限られる…。
茶の湯の人口が増えれば、それだけ需要が高まり、茶道具の価値も相応に上昇していたでしょう。江戸時代の庶民には、なかなか手にすることは出来ない…。「他の器物を茶道具として見立てる」にしたって、それなりのセンスと見識が必要。
困りましたねー、お茶をやりたいのに…。
そこで「茶の湯をよく理解し、風情のある焼き物を作る、当世茶人の手造茶器」が、時代の要請として相当に重宝されていた…と、考えられるのです。
もちろん最初は「自分の楽しみのため」に作陶を始めていたのでしょう。その作品を見た友人が「おっ、コレうまいじゃない!今度僕にも似たようなの作ってよ~」といった感じで、周囲の人間から請われ、評判が広がり、複数回の焼成を行うようになっていったのではないか…。
茶の湯の隆盛と、茶道具の需要供給のバランス問題。これは余技作家の出現と、大いに関係があると思っています。
次回はこの「余技作家」の中でも、謎の部分が多い「香西文京(正木風禅)」をご紹介します。