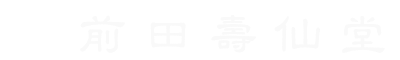海を渡る瀬戸染付04:白雲堂と陶玉園

すっかり間が空いてしまいました。
昨今はインスタグラムの方が更新手軽なもんで…どうもブログの方はサボりがちです。
「やたらとデザインが似通った別々の窯屋」
前回はこれが登場するきっかけとなったと思える、森村組についてのお話でした。


「白雲堂」と「陶玉園」についてまとめます。
白雲堂・加藤周兵衛
森村組の手窯として契約した窯屋のひとつ、白雲堂。
その初代・加藤周兵衛は北新開の陶家・五代定助(京蔵)の二男として生まれ、南新谷の甚兵衛の養嗣子となります。川本治兵衛(二代)の門下生として学んだあと、嘉永5年(1852)に独立し、「白雲堂」と号して染付焼を始めた人です。
明治初年には瀬戸窯元取締役に命ぜられ、後にオーストリア博覧会出品青華磁製造方取締役に任命されたり、愛知県勧業委員にも命ぜられるなど、当時の瀬戸のやきもの業界を代表する一人でした。明治10年に長子・徳七に代を譲り、隠居します。
二代・周兵衛は父の跡を継いで、輸出陶器の制作に精を出します。
その一助となったと思われるのが、森村組です。前回のお話では、森村組の手窯として専属契約を結んだことをご紹介しましたが、このコネクションをいかし、森村組を窓口として英国・米国へディナーセットを生産・販売しています。薄い素地に細い線で絵付けされた洋食器は、大倉孫兵衛などから「海外輸出向け磁器」としてプロデュースを受けていたのではないか、と思われます。
明治30年当初に洋式(ドイツ式)製土方式の完成や、ロクロ仕上げも薄く仕上げられるようになり、また初めは土型(素焼型)・木型などが使われていたのが、石膏型を導入すると作品が精巧になり、かつ量産が可能となりました。
また染付以外にも、これまでの鉄青磁ではないクローム青磁を開発。正円子や上絵付なども熱心に研究し、クローム青磁の上から絵を焼き付ける技術を編み出し、専門の窯屋に焼き付け焼成を依頼していたため、「焼付屋」という名が登場するのは明治30年ごろからだといわれます。
上記のように「父・子」の2代にわたって「周兵衛」「白雲堂」を名乗っており、作品の銘にもこれらの名前・号が入っています。銘のパターンは数種類知られます。
まだ厳密に初代・二代の分類はされていませんが…ほぼ二代の頃の作品と思っていて良いかと思います。(手のかかっている茶道具系はひょっとすると初代かもしれませんが、その証拠が不確かです)
陶玉園・加藤五助
そしてもうひとつ、森村組の手窯として契約した、陶玉園。
もともと五助の家は本業(陶器)の窯として陶業を開始した家でしたが、文政2年(1819)に磁器生産に転業しています。
四代五助は三代の長男として生まれ、文久3年(1863)に家業を継承。瀬戸の中でも比較的早い段階から、輸出向け陶磁器の生産に着手した人物で、常に素地の精選、釉薬の研究、図案・意匠に心血を注ぎ、白磁・青磁の釉薬の上に白盛の浮上模様を描くことを創案するとともに、石膏型導入に尽力、輸出品見本数種を試作するなど、新しい技術・考え方を積極的に取り入れていた人物です。
その意欲的な行動の一つが、森村組との協力関係だとも言えます。前述の周兵衛の一連の作品と非常に似通ったデザインの一群があり、これらは森村組との協力関係の中で、「海外向け」に受けるデザインを周兵衛と共通の絵師(絵付工房)に頼んでいたと思われます。銘の部分だけ「陶玉園」「五助」としてあるため、窯屋の区別がつきます。
単純に個人の名前には帰結できない
分かりやすさ重視で、「加藤周兵衛」「加藤五助」という個人の名前を出しておりますが…。
ある誤解をよく招くので注記しておきます。
現代の人たちの感覚だと、「やきものは、ひとりの陶工の手で作られている」というように感じますが、そうではありません。
非常に小規模な、言い換えれば趣味的な、ある一部の限られた人に向けた焼き物では、そういった「ひとりの陶工が焼き物生産のすべてを担っていること」もあるでしょう。しかしこの時代の瀬戸のやきものでは、そういう事は殆どありません。幕藩体制の崩れた明治以降では、強力なパトロンでもついていない限り、そういうストイックな生産方法は取れません。とても効率が悪いので、食っていけないのです。
- 器のデザインを考案する人
- 陶磁器用の土を精製する人
- 形を使って土を成形する人
- 釉薬を配合する人
- 絵付け、施釉をする人
- 窯で焼成をする人
といったように、工程ごとに分業化しています。これらの差配をするのが周兵衛や五助などの窯屋なのです。窯屋で共通の職人を使っている場合もあれば、ある時期では別の職人に頼んでいることもあるため、「白雲堂」とか「陶玉園」のように銘で作品を分けても、その中で非常にそっくりな作品があったり、全然違う作品があったりするのです。
とはいえ、モノ自体を判別するのに一番わかりやすいのが「高台などに書かれる銘」なので、個人名で説明しているわけです。
今回の話で言えば、器のデザインを考案しているのは恐らく森村組に関わる人物で、輸出向けの器として同じものを窯屋が採用しており、かつ一部の製品は絵付けの職人も同様のところに頼んでいるので、銘がなければその区別がつかないぐらい、そっくりなものが出来ているのです。
まとめ…?
なんだか間が空きすぎて、書いてる僕もぼんやりしてしまっていますが…。
明治時代の輸出向け磁器は、周兵衛、五助だけではありません。他にもいろいろあるのですが、話を広げすぎると収拾がつかなくなるので今回はこの辺で切り上げておきます。