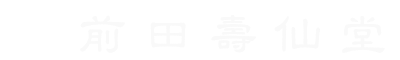郷土の焼き物-豊楽焼・初代利慶

かなり勉強サボってました。(‘A`) さて勉強部屋の再開でございます。
一部加筆修正
2018/10/31 追記
尾張の茶の湯の歴史のあとは何やろう…やはり最近の話題と言えば、アートフェアで講演が行われた「尾張藩の御庭焼」「御深井焼」なんでしょうが…個人的にもう少し勉強してから…というか、奥が深すぎてダイブしきれていない。うーん、どうすっかなぁ、という感じで迷っていました。
美濃でもない、瀬戸でもない、「名古屋」の焼き物
せっかく茶の湯の勉強をしたんで、さらに深く掘っていき、「茶会記研究なんて始めようかしら」と思いつつも、道具の紹介にも繋げたい…。となると、やはり豊楽ですかね。幸い、手元にこんな素敵な資料があることですし。
参考書籍の紹介
- 「名古屋のやきもの 豊楽焼」 名古屋市美術館 平成7年
- 「富士見の里 昔の前津 ―江戸から昭和―」 名古屋市博物館 平成18年
名古屋で楽焼が始まるのは江戸中期から
江戸中期~後期。茶の湯のビックウェーブが名古屋に押し寄せ、「よっしゃ、ワシもお茶やるぞー」と町方の人々まで茶の湯を嗜むようになります。
すると何が起こるか。この地域における、茶道具の需要が増大したと考えられます。
まず尾張藩では開府当初から焼き物の生産に力を入れており、主にそれは「贈答用」として、様々な交流を円滑にするための道具として重宝されてきました。(これが御深井焼の始まり)瀬戸・美濃の窯場を整備し、藩の要望で様々な陶器が生産されました。もちろん茶陶も生産されていたでしょうが、まずこういったものは「大名や寺院への進物」であり、当時の市井の人々の手になかなか渡らないものでしょう。
当時、茶の湯の最先端都市は「京」と「江戸」。特に京は歴史があり、その周辺では様々な焼き物が生産されていたほか、宮廷文化と結びついて「京焼」が発達し、優美な茶道具が多数生産されていました。
ただ、それらを尾張に持ってくるのもコストがかかる。しかし安価であれば需要はある。となると、地元での窯業にも影響が及ぶわけです。
幸い、尾張には昔から窯業が盛んな土地が豊富。瀬戸、美濃、常滑。さらには材木の流通拠点・経路として熱田~堀川が整備されており、燃料となる薪の入手も比較的容易だったでしょう。旧来の窯業も活発になったでしょうし、さらに消費地の近くで作ればコストも下がってさらに売れるのではないか…。
こうした背景をベースに流行したものの一つが、豊楽焼だと考えられるのです。
街中に窯場?
当初、豊楽焼の窯があったのは、かつて存在した「大池」という池の畔。
どこにあったかというと、現在の上前津。GoogleMAPで現在の地図を見てみると……。
ピンポイントで「前津児童館」が指定されてますが、正確にこの場所が窯場というわけではありません。あくまで古地図から推測する大体の位置です。
すぐ近くに地下鉄・上前津駅があり、そのさらに西は大須の繁華街(今じゃオタクの町として、様変わりしちゃいましたねー)
ちなみに我が母校・前津中学校がすぐ北に。いやー、懐かしいなぁ…。夏休みの自由研究で「名古屋の焼き物」を発表して、中学生らしからぬ渋すぎるテーマゆえに、「マエダくん、キミ…ホントに自分でやったの?」と怪しまれましたねー。
まあ弁解の余地もないほどに、大半を父がやったんですけどネ。(´・∀・`)ゝ
閑話休題。今度こそ、自力で自由研究ッス(笑)
大体、この東側(現在の中区千代田2丁目~3丁目あたり)に「大池」という巨大な溜池が存在していました。現在でこそ、大須の東側、マンションなどが立ち並ぶ普通の街中ですけど、かつては何にもない原っぱでした。
そして、このあたりはもともと低湿地であり、深ーく掘ると水が出てくるんです。(※前中卒業生なら、校庭の水ハケの悪さはよく知ってるハズ)そこで、田んぼのための灌漑用水として、元禄期にこの村の百姓たちが総出で掘って作ったのが、この大池なのです。池の水が麹のように澱んでいたため、「麹が池」とも呼ばれています。
江戸期は農地が広がっていた地域ですが、大正期には町の発展とともに大池は埋め立てられ、「大池町」という町の名前の由来になっています。
立地的には、瀬戸・美濃よりも、ずっと名古屋の城下町に近いですよね。
この池の畔に窯を築いて陶器の制作を始めたのが加藤利慶。豊楽焼の初代です。
御焼物師 加藤利慶
初代・利慶は宝永5年(1708)生まれ、寛政8年(1796)歿。当時としてはかなり長寿の人。
文献にこの名はあまり残されていませんが、歴代の豊助が先祖のことを調べ、それをまとめたものが「一楽會誌 二」に掲載されており、初代の生没年もそれに拠っています。
「一楽會誌 二」は大正12年に行われた、尾張の古陶を紹介する「陶器陳列会」の出品目録。その陳列会に初代・利慶作の「青楽名刺」が出品されており、これはいわゆる「陶器でできた名刺」で、表面に「寛政六寅八月十九日 奉上御神前 御焼物師加藤利慶」の銘が彫られているのです。
「御焼物師」という肩書きですが、これは尾張藩に焼き物を生産して納めていた人だったと考えられます。近年の発掘調査により、「利慶」印のある徳利片と思われる資料が尾張藩の江戸上屋敷跡から見つかっているため、利慶と尾張藩の関係はほぼ間違いないと考えられています。藩に献上する焼き物を作るというところからも、技術的にも当時から高い評価を受けていた人物だと思われます。
また利慶は萬松寺(現在も大須にあるお寺)のすぐ南側、「カクレサト(隠里)」という場所に住んでいました。(後に二代・豊八がこの家に窯を移します。)
利慶の作品
あまり数は残されていませんが、利慶作とされる陶器は現在にも伝わっております。
土風炉、灰器、菓子器、蓋茶碗などなど。制作時期などの詳細こそ分かっていない初代ですが、時代背景から察するに、やはり増大した茶道具の需要に応えるべく、食器類と平行して茶陶も制作していたと考えていいように思います。
利慶の始めた焼き物は消費地への輸送コストが下がる分、濃尾地方で言うところの「お値打ち(お買い得)」で評判になったことが想像されます。名古屋の人たち、「お値打ち品」って大好きですもんね。
消費地の近くで生産し、コストダウンを図る。これが当時、そこまで考えて行ったことなのか、その真意までは分かりません(自宅の近所で焼いたら、たまたま上手に焼けて、立地や輸送手段などいろいろ条件がそろったという、ただの偶然なのかもしれません)が、結果的に繁盛したおかげで、二代・豊八へと受け継がれていきます。